【フレイル予防!】簡単にできる生活習慣のコツ◎管理栄養士が教えます!
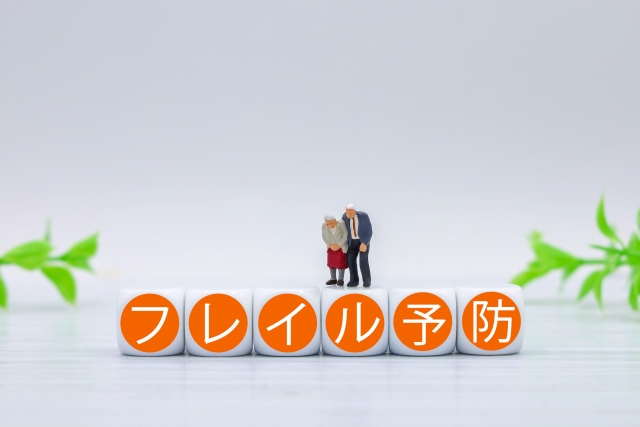
健康寿命を延ばすためには日々の健康管理が大切です。みなさんは最近よく耳にする“フレイル”をご存じですか?今回はフレイルについて解説し、フレイル予防のための運動についてご紹介します。
2025年07月14日
フレイルとは?
フレイルの解説

フレイルは、Frailty(フレイルティ)が語源となっていて、加齢に伴って心身が老い衰えた状態のことを表現しています。フレイルは高齢期に陥る場合が多く、健康な状態と介護が必要な状態の中間に位置していることを示しています。このような状態は、生活の質を低下させるだけではなく、健康寿命を短くしてしまう原因にもあるため早めの対策が大切です。
フレイルになるとどうなる?
フレイルになり、対策しないと介護が必要な状態に陥る可能性が高くなります。 ・身体的な虚弱(フィジカルフレイル):ロコモティブシンドローム、サルコペニアなど ・社会性の虚弱(ソーシャルフレイル):閉じこもり、孤独など ・こころの虚弱(メンタルフレイル):うつ、認知機能低下など ・口腔内の虚弱(オーラルフレイル):咀嚼嚥下機能の低下、活舌低下など 心身のさまざまな部分で現れてきます。自分自身も周囲の関係者も早めに気付いて、栄養・運動・社会参加などの対策を行いましょう。
フレイルの基準
当てはまる場合は要注意

フレイルを見極める基準の例をご紹介します。当てはまるところがないかチェックしてみてください。 1.体重減少:意図しない体重減少(6か月間で2㎏以上) 2.疲れやすい:(ここ2週間)わけもなく疲れたような気がする 3.歩行速度の低下:通常歩行速度<1.0m/秒 4.握力(筋力)の低下:男性<28kg、女性<18kg 5.身体活動量の低下 下記の2つのいずれも「していない」と回答 (1)軽い運動・体操をしていますか? (2)定期的な運動・スポーツをしていますか? 上記1~5項目のうち、3項目以上該当:フレイル、1、2項目該当:フレイルの前段階、0項目は健常とされています。 ※日本版フレイル基準より
その他のチェックポイント
両手の親指と人差し指で輪を作り、効き足でない方のふくらはぎの一番太い部分に指輪っかを当て、サルコペニアの危険度をチェックする「指輪っかテスト」があります。また、栄養・運動・社会参加について11項目をはい・いいえで回答する「イレブンチェック」という方法もあります。
フレイルを予防するためのポイント
多方面からのアプローチ
フレイル予防のためには、1つの項目だけではなく栄養・運動・社会参加などさまざまな方面から対策をすることがポイントです。今回は、フレイルを予防するための運動や身体活動に関するポイントをご紹介します。
座りっぱなしの時間を今よりも短くする
仕事が落ち着き、自宅にいる時間が長くなると座っている時間が長くなります。いざ歩数を測定してみると、驚くほど少ない!と気付くかもしれません。厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023年」では、高齢者は1日約6,000歩以上、成人では1日約8,000歩以上の歩行を推奨しています。急に歩数が増やせない場合は、まずは今より+1,000歩を目指してみてください。
ウォーキング

運動習慣がある人もない人も気軽に始められるウォーキングは、特別な運動器具がなくても実施できるのでおすすめです。頻度や時間も自分のペースで調整できるので、レベルに合わせて始めてみましょう。 ゆっくり歩きよりも、少し息がはずみ、うっすらと汗ばむ程度の速歩がおすすめです。
水中運動
腰や膝への負担が少なく、泳げない方でも水中歩行などを行えば効率よく運動できます。プールに行くまでの道のりも歩数を増やすことができるので一石二鳥です。
運動教室に参加する

仲間づくりを兼ねて、公民館や体育館などで行われている地域の運動教室に参加するのもおすすめです。得意な運動を選んだり、今までやったことのない運動にチャレンジしてみるのもよいですね。
まとめ
運動する前は体調チェックを忘れずに
いかがでしたか。フレイル予防のために皆さんの生活習慣を見直すきっかけになるとうれしいです。安全に取り組むために、運動前は必ず体調チェックを行ってから実施しましょう。転倒にも注意しつつ、医療機関に受診している方は必ず医師の指示のもと実施するようにしてください。 【参考資料】 ・厚生労働省. 身体活動・運動の推進. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html)閲覧日:2025年1月11日 ・公益財団法人長寿科学振興財団. サルコペニア・フレイル(https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/index.html)閲覧日:2025年1月11日
【やせ習慣が身につく】管理栄養士が食生活をコーディネートするアプリって?
まずは無料でスタート♪食事を撮るだけ、プロから食事のアドバイスが届く!
- 専属の管理栄養士がダイエットをサポート
- 食制限なし!正しく食べて身につく「やせ習慣」♪
- 管理栄養士が、写真を目で見て丁寧にアドバイス。AIではありません!
- 「あってるかな?」そんな食事のお悩みを正しい知識でアドバイス
著者
丸山 まいみ(管理栄養士、公認スポーツ栄養士)

家庭の料理を通じて食に魅力を感じ管理栄養士となる。 診療所での栄養指導、特定保健指導、スポーツ選手に対する栄養教育に携わる。 現在は、ひとりひとりの背景に合わせ、食の楽しさや可能性を伝えるためフリーランスとして活動中。






